
医師より腎臓病の所見が出た場合、必ず食事に関する指導や指示があるはずです。病院によっては管理栄養士が献立のアドバイスなどもしてくれます。
同じ腎臓病でも、急性腎不全(急性腎臓病)と慢性腎不全(慢性腎臓病)とでは、食事療法の内容が若干異なります。摂取上限値や水分制限など、ネットの情報だけを鵜呑みにせず、腎臓病を専門としている医師や管理栄養士から正しい情報を得るよう気をつけてください。
急性腎不全は、腎臓の機能が外的要因によって急激に悪化する病気。タイプによって治療法が異なりますが、正しく治療が行なわれれば、腎臓の機能が回復する可能性もあります。急性期と回復期では制限されるたんぱく質や食塩の量が異なりますが、高齢者や肥満の人は摂取エネルギー量も減らす必要があります。
慢性腎不全の場合、どのような治療をしても「完全に腎臓病が治る」ということはありませんが、薬物療法や食事療法によって、これ以上腎臓の機能が低下しないように維持したり、低下するスピードを遅らせたりすることができます。
急性腎不全(急性腎炎症候群)は、外傷性ショックや脱水症、薬の副作用などさまざまな原因により、急激に腎機能が低下した状態です。症状に合わせて薬剤の投与や点滴(補液)などと同時に食事療法を開始します。
食事療法は急性腎不全の患者にとって、もっとも重要度の高い治療。急性期患者用のガイドラインに沿って、総エネルギー量やたんぱく質量、塩分量、場合によりカリウム量を制限することになります。急性腎不全の特徴として、発症期から乏尿期(尿が出ない)、利尿期、回復期と状況が変わっていきます。その時期に合わせて水分制限など食事療法の内容が変わってきます。
急性腎不全の場合は入院して治療することが多いので、食事療法も病院で提供される食事で問題ないはず。退院後も回復期の延長上に療養食を家庭で作ることになりますので、退院前に栄養相談を受け、管理栄養士からどのような食事療法がよいのか説明を受けるようにしましょう。
慢性腎不全は、急性の腎疾患と異なり薬物投与や食事療法を行なっても、完治するということはありません。治療の目標となるのは「これ以上腎機能の低下が進行することを予防して、腎不全末期の人工透析(透析療法)への移行を少しでも遅らせるように現状を維持する」こと。慢性腎臓病の進行度合いによっては、運動や日常生活に対する意識を行き届かせ、体調を管理していくことが重要なポイントとなります。
慢性腎不全にもさまざまな原因がありますが、最近は糖尿病との合併症である糖尿病腎症や、痛風とほとんど同じ原因で病状が進行する痛風腎、高血圧により動脈硬化が進んだ結果生じる腎硬化症など、生活習慣病と腎臓病には密接な関係性があります。
食事療法については、たんぱく質や塩分、カリウムやリンなど病状に合わせて調整することが大切です。

家庭で腎臓病食を作るためのガイドラインや「腎臓病食品交換表」などを使って、毎日の食事を管理していくことが大切です。基本的には医師からの指示で食事療法の方針を決定します。控えたほうがよい食材もありますが、カロリーアップや、肉や魚、卵、大豆製品などのたんぱく質量を意識したり、カリウムを減らすために野菜の下準備など、調理法のコツをおぼえたりすることで、毎日の食事が組み立てやすくなります。
たんぱく質や塩分調整には、低たんぱく食品や減塩調味料などを上手に利用することで食事の幅も広がります。慢性腎不全の場合「いつまで」という期限がありませんが、食事療法の基本をおぼえることで、家族やご自身にかかる負担を減らすことができます。
たとえば糖尿病性腎症などは糖尿病の食事療法では、それまでの糖尿病の食事の基本であったことと、腎臓病の食事療法の方針が変わるため、「何を食べたらいいのかわからない!」と悩んでしまうこともあると思います。そんなときはひとりで悩みを抱え込んでしまうよりも、すぐに医療機関や専門家に栄養相談するようにしましょう。
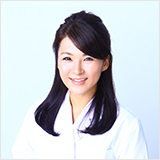
宮澤 かおる(管理栄養士・健康運動指導士)さんからのアドバイス
「病院の医師や管理栄養士に指導されて食事療法を始めると、最初はとてもストレスを感じてしまうと思います。でもじつは、慢性腎臓病だからといって普通の食事を食べてはいけないのではなく、食べる量や塩分に気をつけて今の病気が悪化しないように気をつけましょう、ということなのです。もしも外食でたんぱく質や塩分を摂りすぎてしまった日があったら、その翌日は制限食で塩分やたんぱく質をコントロールするなど工夫すれば問題ないのです」
腎臓病の食事療法には、守るべき重要なポイントがいくつかあります。急性腎不全なのか慢性腎不全なのか、腎臓病の種類によって気をつけなければいけないポイントが若干異なりますが、ここでは腎臓病という大きなくくりで食事療法の全体像について整理しておきたいと思います。
繰り返しになりますが、慢性腎臓病は生きている限り食事療法を継続することが大切です。ですから、腎臓病用食がある食事宅配サービスなどを上手に活用して、食べる楽しみが失われないように工夫していくことが病気と向き合うコツでもあります。お金がかかることではありますが、時間や精神的苦痛を軽減させるための必要経費と考えて、前向きに取り入れていくことをおすすめします。
腎臓病食で難しいのは、これまでカラダにいい食べ物だと思っていた食品や食材のいくつかは、腎臓病患者にとって「カラダに負担になる食べ物」になってしまうという点。
たとえば慢性腎不全の進行度合いによってたんぱく質制限やカリウム制限が入りますが、カラダによいと今までしっかり取っていた魚や大豆製品などはたんぱく質を多く含みますし、野菜や果物、ナッツ類などはカリウムを多く含んでいます。こうした食材は、食べる量を調整していくことになります。

腎臓病という病気の食事療法のうち、いちばん顕著なものが「たんぱく質の摂取量を制限する」ことです。たんぱく質は、肉や魚、卵、大豆製品などをはじめ、さまざまな食材にはいっています。健康なときに意識することはないと思いますが、じつはたんぱく質を分解していらない老廃物を体外に排出するのは、腎臓の役割。
たんぱく質は、カラダをつくる上で重要な栄養素ですが、腎臓に問題が見つかったときは、腎臓への負担を軽減するためにたんぱく質の摂取量を制限することが、食事療法の重要なポイントになります。
炭水化物や脂質は体内でエネルギーとして利用されたあと、その老廃物は尿や呼吸などから排泄されます。ところがたんぱく質は代謝されたあと、体に有害な老廃物を作り出してしまいます。尿素窒素(BUN)や尿酸などがその有害物質にあたりますが、たんぱく質を過剰摂取し続けると腎臓が有害物質を排出しきれなくなり、体内に老廃物が蓄積して尿毒症などになってしまいます。そのため腎臓病と診断されたら、腎臓の負担を軽減するためほとんどの場合、食事療法ではたんぱく質の摂取量を制限する必要があるのです。
上限摂取量は体質や体格、クレアチニン(クレアチンが代謝されてできた物質)の上昇などによって異なるため、医師や管理栄養士の指示に従って食事療法を実施していきます。通常は体重1kgあたり、0.6~0.8gに制限します。たとえば、体重が60kgの人なら、1日に摂取できるたんぱく質の量は36g。非常に少なく感じますが、低たんぱく食品などと上手に活用して工夫します。
なお、たんぱく質を制限すると1日の総エネルギー量が不足してしまうので、炭水化物や糖質、脂質などで補うようにします。「腎臓病食品交換表」などを活用して計算するところからスタートです。

次に重要なのが食塩(ナトリウム)の制限です。体内の余分な塩分を排泄するために腎臓に大きな負担がかかり、腎機能が低下すると体内に水分を溜め込むようになり、むくみの原因となります。また塩分の過剰摂取によって血管を流れる血液量が増えていることから、血圧を上げて血液を循環させる必要に迫られるため、高血圧になってしまいます。血管が酷使され傷むため脳卒中や心筋梗塞などのひとつの原因になります。
腎臓機能が低下すると高血圧になりやすく、高血圧になれば心・血管病(心臓・血管の病気の総称)を呼び込むことになりますので、まさに合併症が合併症を呼ぶことに。腎臓病と高血圧にはこのように密接な関係があることを知る必要があります。
1日の食塩摂取量を6g未満に制限しますが、急性腎臓病の場合などは時期によって制限基準が異なりますので上限摂取量についても主治医や管理栄養士の指示のもと、過不足なく摂取することが大切です。

腎臓の機能が低下すると、カリウムやリンを尿として排せつする機能も低下し、血中のカリウムやリンの濃度が高くなってしまいます。健康であれば1日に摂取したカリウムのうち、約90%は尿として、残りは便から排泄されますが、腎機能が低下してカリウムが排出されなくなると高カリウム血症になり、不整脈や嘔吐などの症状に見舞われます。
ほとんどの腎不全はこの高カリウム血症をともないます。またリンの濃度が高くなり高リン血症になってしまうと、骨がもろくなったり、動脈硬化を引き起こしやすくなったりします。
カリウムの摂取目安量は、1日1,500mg以下に制限します。カリウムが多く含まれる食材は、野菜、果物全般です。バナナ、夏みかんやメロン、スイカなどの果物類に多く含まれます。野菜でもサトイモやカボチャ、白菜、キャベツ、カブをはじめ、カリウムが多く含まれます。野菜を濃縮してつくる野菜ジュースやスムージーなども注意が必要です。
カリウムは水に溶け出る成分なので、野菜などは、刻んだあとに水にさらしたり、蒸す調理法よりも茹でこぼしたりすることで、カリウムを減らすことができます。またサラダを作るときや焼く前、汁物に入れる前もひと手間加えると、カリウム量を調整することができます。果物はりんごなど一部のものをのぞき水にさらすことが難しいので、食べる量を調整したり、缶詰などの加工品を利用したりするとよいでしょう。
魚介類に多く含まれるリンについても、医師の指示に従って摂取量を減らすようにしてください。
ただし、急性腎不全の場合は乏尿期、利尿期、回復期と治療のステップごとに制限の度合いも異なります。自宅療養中の食事療法については医師や病院の管理栄養士のアドバイスに従って食事療法をすることになります。これまで健康にいいからと積極的に摂っていた食品や飲み物でも、カリウムやリンが多く含まれていないか、ひとつずつ確認するようにしましょう。

たんぱく質を制限すると、どうしてもエネルギー(カロリー)が不足してしまいます。エネルギーが不足すると、筋肉など体内のたんぱく質を燃やして使うようになってしまうため、腎臓に負担がかかることになります。せっかくたんぱく質の摂取量を減らして腎臓を休めようとしているのに、これでは意味がありません。ですから、「腎臓病食品交換表」などを参照しながら、「低たんぱく・高カロリー」の献立を考える必要があるのです。
基本的には炭水化物などの糖質と、油脂などの脂質でエネルギーを補うことになりますが、その際に気をつけなければいけないのは、たんぱく質を含む食品や調味料があると意識することです。ごはんやパンなどの炭水化物には、たんぱく質が含まれますので、砂糖や油脂を使った調理法を上手に取り入れていくことがコツです。
中鎖脂肪酸油を使用したパウダーなども活用できます。また、治療食用に「カロリーアップ食品」として、ゼリーやビスケット、成分調整チョコレート、低リンミルクなどの食品がありますので、毎日の食事が楽しめるように適宜取り入れるとよいと思います。
油であればバターやマーガリンは避け、サラダ油やオリーブ油を使うようにしましょう。中佐脂肪酸油を使用したパウダーなども活用できます。また、食事療法用に「カロリーアップ食品」として、ゼリーやビスケット、成分調整チョコレート、低リンミルクなどの食品がありますので、毎日の食事が楽しめるように適宜取り入れるとよいと思います。

むくみがある場合などは水分量を抑える必要がありますが、腎不全の患者の場合、基本的には水分保持能力が低くなっているので、脱水症に注意しなければなりません。つまり、症状や腎臓病の種類に応じて水分量を減らしたり、増やしたりしなければならない、ということです。
たとえば急性腎不全の場合、乏尿期は前日の尿の量によって摂取してよい量が決まりますし、薬物療法によって一時的に尿量が増える場合など、観察しながら水分量を調整する必要があります。
水分には食べ物から得られる水分も含まれますので、上限摂取量ギリギリまで水や飲料を摂取するのではなく、食べ物からの水分も計算に入れながら調整するようにします。飲む水はしっかり計量し、食事の際は十分に水気を切って食べるなどの工夫をするとよいでしょう。ただむやみに制限せず、必ず医師の指示に従いましょう。
腎臓病食は、入院しているときには、目や口で量や味付け、どんな食材を使っているのかを覚えるようにしておくことをおすすめします。そして大切なのは退院後の自宅療養から日常生活に戻ったあと。腎機能が低下した場合は、継続して食事療法を行います。
これまで食べたいものを食べたいだけ、がまんすることなく食べてきたという人にとって、食事療法でさまざまな制限がかかってしまうのは慣れるまで大変です。また治療食を作らなければいけない家族の負担もあると思います。
新たな国民病ともいわれる慢性腎不全ですが、できるだけ透析療法への移行を遅らせたいところ。食事療法によっていまの腎臓の状態を維持し、病状が進むことを予防しなければならないのです。
成分調整食品も通販サイトで手軽に購入できますし、腎臓病食の宅配サービスもたくさんあります。自力だけでなくこうした他力も頼って、なるべくおいしく、楽しく食事ができるように取り組んでいけるとよいと思います。
当サイトは「食と腎臓病について考える会」が管理・運営している、腎臓病の基礎知識と役立つ情報をまとめたポータルサイトです。掲載しているコンテンツに関しましては、できる限り最新の情報を元にオリジナルの記事を作成しております。ただし医療機関や専門機関ではありませんので、疾病に関する専門的な相談や依頼は承っておりません。
また当サイトに掲載されている情報のご利用・ご活用に関しましては、自己責任でお願いします。万が一、掲載されている情報でなんらかの損害が発生したとしても、当サイトでは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。